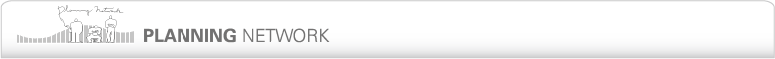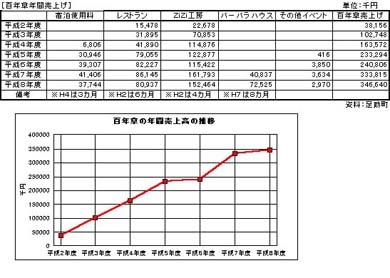|
�@�n��̊T���ƒn��Â���̂�������
�@�������́A�L�c�s�Ǝ��ߋ���(�Ԃ�30��)�ɂ��邱�Ƃ���A���݂́A�A�Ɛl���̂R���̂Q���g���^�����Ԋ֘A��Ђɋ߂�u�s�s�ߍx�ʋΎR���v�ƂȂ��Ă���B���������̐̂́A�����E�O�͂Ɣ��Z�E�M�B�����ԁu���̓��v�Ƃ��āA�l�ƕ����̉��������ʂ̗v�ՂƂ��ĉh�����B�����n���������������u���n�X���v�Ə̂��A�X�������̒��̒��S���ɂ͍]�ˎ���������A�����E�吳�E���a�̏����ɂ���ꂽ�Â��ƕ��݂������Ă���B
�@�������̖{�i�I�Ȓn��Â���́A1970(���a45)�N�́u�ߑa�n��̎w��v����͂��܂�B1970�N��̉䂪���́A�f�B�X�J�o�[�W���p���ɑ�\�����u�ό��u�[���v�ł��������A�����̂܂��Â���͗��s�̈��Ղȃ��W���[�J�����u�������A���n��Ɍւ����̂�������Ǝ����B�Ŏ咣�ł���悤�Ȍ`�Ŏ�葱���邱�Ƃ��d�v1)���Ƃ̍l���̂��ƁA�s�s�Ɍ}�������n��J����ے肵�A�Ǝ��̒n��Â����W�J���邱�ƂƂ����B
�@�R�̐�����`���鐶���������قƂ��Ắw�O�B�������~�x�A���S���́w�����ݕۑ��x�A����Ɋό��ƕ����ƕ��Y�Ƃ��Z�������w�S�N���x�A�n��̃V���{���Ƃ��Ắw������x���A���X�̎{�݂����܂�A�n���Z���̐����Ƌ��������u�W�q�^�̒n��(�𗬊ό�)�v�ւ̓r���m���ɐi��ł���B
�@�R���ɑ傫�ȃ��}����Nj������w���������}��(��Q�������������v��F1984�N)�x����A�𗬏d���^�̂܂��Â����ڎw�����w�����V�����O�����|���z��(��R�������������v��F1996�N)�x�ւ̈ڍs�́A�l�����I�̒n��Â���̎��т𒅎��ɍs������Ɉʒu�Â��A����Ȃ�u�W�q�^�̒n��(�𗬊ό�)�Â���v�ւ̓r��W�J���悤�Ƃ��Ă���p�������Ɍ��邱�Ƃ��ł���B�@���g�b�v
�A�n�������̓���
�@�s�s�}���^�̒n��Â���ł͂Ȃ����n��̌ւ聄�����������n��Â���́A�w�ۑS���J���ƐM���钬�E�����x�Ƃ����n��Â���̃L�[���[�h����i�߂���B�L�[���[�h�Ɍ����鐸�_���u�����̒����݂�����v�̔����ɂȂ���A�����ݕۑ��^���A�����i�ω^���ւƓW�J�����B�܂��A��P��́u�S�������݃[�~�v�𑫏����ŊJ�ÁA�P�O�O�l����w�ҁA���z�ƁA�R���T���^���g�A�}�X�R�~�W�҂��K��A�Q���҂Ƃ̌𗬂̒�����l�X�Ȓq�b��B�����ł��l�ރl�b�g���[�N2)���A�����̑��̏W�q�{�݂ƍl������u�O�B�������~�v�̍\�z���`�Â���ɂ������Ẳ����c�ƂȂ�B
�@�܂��A�n��Z���ɑ��ẮA�ړ������n�捧�k��i�t�H���\���j�����p�����ĊJ�Â��A�s���̍l����n��Â���i�v�����āj���A�s�[�����A�����Ƌ��͂����߂Ă���B�𗬏d���̒n��Â����i�߂�s���ɂƂ��āA�u�S���I�ɎY�Ƌ����i�ޒ��ŁA��Ƃ�H��̗U�v�͌������ɂ���A�N�ƉƐ��_�̂���l���x�����Ēn����̐V�����r�W�l�X��W�J���邱��3)�v�̍l�������L���������A�Q�����Ă��炤���Ƃւ̊��҂��A���̈ړ������n�捧�k��̎�g�݂̒��Ɍ��邱�Ƃ��ł���B
���g�b�v
�B�W�q�̂��߂̏��i�̓���
�@�������̏��i�́A���s�ɕΏd�����Ǝ��̒n��Â�����u��������̂ł���A�w�O�B�������~�x�Ɓw�����ݕۑ��x���P�e�̏��i�Ƃ��āA��Q�e���w�S�N���i�����E�ό��E���Y�̕����{�݁j�x�A�����đ�R�e���w������i�n��̃V���{���j�x�ƁA���X�ƓƎ��̏��i����W�J���Ă���B�����͂�������A�`���E�����E�R���������̒n�掑�������p���A�u�n��̌ւ�v�Ɓu����҂̐��������v����т����e�[�}�Ƃ��ď��i���������̂ł���A�P�Ȃ�ό��{�݂Ƃ͗l�����قɂ���B
�@���̂����w�O�B�������~�x�̏ꍇ�A�b�艮�A�Y�Ă��A���������̒n��̒��Ŏ�d�������ۂɍs���Ă���Ǝ��I�����A�Â����Ƃ̈ڒz�ⓖ�����霂�����{�݂̐������ɂ���āu�����������فv�Ƃ��ĎR�̐�����`���Ă���B�܂��{�ݓ��ł́A�Z�p������������ҒB���ւ�������ē����A���̋Z�p������֓`���鋒�_�{�݂ƈʒu�Â��铙�A�n��̌ւ�ƍ���҂̐��������i���U�����j���{�ݐ����̃e�[�}�Ƃ��Ă���B�܂��A�w�S�N�w�x�́A�u�����v�Ɓu�ό�(��)�v�Ɓu���Y�v���R���Z�v�g�Ƃ��������I�𗬋��_�ł���A�n��̍���҂̂��߂̕����Z���^�[�ɁA�u�n���H�[(�y�h�y�h�H�[)�v�Ɓu�p���H�[(�o�[�o���͂���)�v4)�Ƃ݁A����҂��ٗp���ā����������Â��聄��W�J����ƂƂ��ɁA�n��̓��Y�i���i�����u�����h�j��}���Ă���B
�@�����̎{�ݐ����͂����܂Œn��Z�������ɂ��A���̎d���̗l�q��V���Ȋό������Ƃ��đn�o����ƂƂ��ɁA�𗬎Ҍ����{�݂Ƃ��ă��X�g������z�e�����ꃖ���ɏW�ϗ��n�����Ă���B�@���g�b�v
�C�p���I��g�݂̓���
�@�������̒n��Â���́A�n��Z�����u���y�ւ̌ւ�v�Ɓu���i���}���j�v�����Ă�悤�Ɏ�g��ł�����̂ł���A�u�𗬐l���v�͂����܂ł���i�Ƃ��Ă�������5)���A�������̑����v�悩����ǂݎ���B�܂��A���y���⌚�ݏȁA���z�w��A�T���g���[�����ܓ�����܂��Â���̎��H�̕]������6)�A�����̎��܂�ƂɁA����܂ł̐��X�̒n��Â���̎�g�݂�����ɒn��ŋ��L���邽�߂ɁA�u�𗬊ό��̐��i�v�u�𗬏d���^�Y�Ƃ̑n�o(�N�ƉƐ��_�̏���)�v����ڎw���Ă���B
�@����ɁA�n��Â���́u�l�Â���v�ł���Ƃ̍l���̂��ƁA21���I�̑����̊ό����l����c�̂Ƃ��āu�`�s�Q�P��y���v��g�D���A�u�A�b�g�Q�P�ʐM�v��u�g�s�b�N�X�����v���̒n��~�j�R�~���������I�ɔ������A�n��Z���ւ̌p�������A�s�[���ɐS�|���Ă���B
�@����܂łɂ��������悤�ɁA�������ł́u�q�b�����݂������𗬂̖��́v��n��Â���̋M�d�Ȏ�i�ƔF�����Ă���Ƃ͂������̂́A����܂ł̒n��Â���͒n��Z���Ɏ���u���A��Z�l���ƌ𗬐l���Ƃ��������钆�Œn��̊��͂��ێ��E���コ���Ă������̂ł���A���̎�@�͍���Ƃ��n��ɍ��t���ēW�J�������̂ƌ�����B�@�@���g�b�v
�@
�@
�m�Q�l�����n
�@�ؐM�s�i1996�j�w��o�c����o�̂܂��Â���E�������x�A���i No.5�@�o38�`�o47
�A�������i1996�j�@�w��O�������������v�恃�����V�����O�����v��|1996��2005���x
�B��ҏW���i1995�j�w����҂��������p���H�[�u�o�[�o���͂����v�x
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������1995�N11���������G���A���傤����
�C����i1982�j�w�����̒��Â���x�A�����ό�1982�N1�������o10�`14���A(��)���{�ό�����
�D����i1983�j�w�V�l�p���[�̊��p�Ɠ`�������̕����x
�@�@�@�@�@�����ό�1983�N9�������o35�`38���A(��)���{�ό�����
�E�����ό��ҏW���i1983�j�w���������Â���|���͂���ό��n�Ƃ́x
�@�@�@�@�@�����ό�1983�N10�������o25�`39���A(��)���{�ό�����
�F�����ό��ҏW���i1984�j�w�����̒����ݕۑ��x
�@�@�@�����ό�1984�N10�������o43�`47���A(��)���{�ό�����
�G���V����i1991�j�w�������~�N��蕨��x
�@�@�@�����ό�1991�N8�������o36�`39���A(��)���{�ό�����
�H���V����i1989�j�w�O�B�������~�̌o�c���l����x
�@�@�@�����ό�1989�N2�������o21�`26���A(��)���{�ό�����
�I��t�����i1996�j�w�����n���y���y���H�[�E�p���H�[�o�[�o���͂����x
�@�@�@�n��̊��͂Ɩ��͇B�u���킢�v���o117�`122���A���傤����
�J�����i1997�j�w�q�g�����m�������[���R���͎��Ɋy���x
�@�@�@�ό�����No121�����o2�`8���A(��)���{��ʌ���
�K�Ԑ����v�i1995�j�w���U�������P�����x
�@�@�@�P���l�E����߂��܂����o142�`151���A�j�s�b�����o��
�L��ҏW���i1994�j�w�����E�ό��E���Y�̑������_�x
�@�@�@������1994�N5�������o22�`23���A���傤����
�M��싱���i1993�j�w�͘F���̕������u�����������فv�̌��_�x
�@�@�@���Ȃ��̒��큃�o184�`200���A��������o��
�N�T���C�ҏW���i1995�j�w�������|���p���Ղ̕x�����Ɂx
�@�@�@�u���̒��v���䂭���o80�`87���A���w��
�O�����@�O�i1980�j�w�����|�ߐ��̉��ғ��A�����݁A�������~�x
�@�@�@���j�̒��Ȃ݁|�֓��E�����E�k���ҁ��o106�`110���A�m�g�j�u�b�N�X
�P�܂��Â���ҏW���i1990�j�w���j��k��܂��Â���|�������̎��݁x
�@�@�@The�܂��Â���View�@No7�����G���A���@�K
�Q�������̑�����i1990�j�w��B�������~��10�N�x�A������
�@���g�b�v
�@
�m���߁n
�P�j�����@�iP38�j�B
�Q�j�u1977(���a52)�N�A��P��S�������݃[�~���������ƁA�L���i���É����C���j�ŊJ�Â��ꂽ�B�S������A�w�ҁA���z�ƁA�R���T���^���g�A�}�X�R�~���X�P�O�O�]����������K��A����̑����̂܂��Â���ɗ^�����e���͑傫�������B���������^�����A1980(���a55)�N�S���ɊJ�ق����O�B�������~�̕z�ɂȂ������Ƃ��������Ȃ��v�i�����@P39�j�B�k�����@�l�ɂ��ƁA�O�B�������~�̍\�z�̎����Ɍ������Ȃ����̂Ƃ��Ē����ݕۑ�������Ƃ��A���̒����ݕۑ��Ɛ�̑S�������݃[�~�Ƃ̌W���ɂ��Ď��̂悤�ɋL���Ă���B
�u��P���݃[�~�Œm�荇�����n�ӌ��z�v�������̉���n�߁A�Ⴂ���z�v�҂̏����A�w���ɕ����Ƃ��낪��ł���B�ނ�́A�q�~�̕ۑ��I�Đ��i�A�C�r�[�X�N�G�A�j����Ă�Ȃnj��z�E�ł͂悭�m���Ă���v�i�����@P40�j�B�@���g�b�v
�R�j�w��O�������������v��x�ł́A�������̎�v�ۑ�ƑΉ��̕����Ƃ��āA�@�l�������ƍ���ɓK�Ȏ��łA�A�𗬏d���^�̎Y�Ƃ�W�J����A�B�L���ɕ�点�鐶����Ղ𐮂���A�C���ƒ��a�����v��I�ȓy�n���p��i�߂�A�D�����ƍs���̃p�[�g�i�[�V�b�v����Ă�̂T�������Ă���B�u�𗬏d���^�Y�Ɓv�̍��̒��ŁA�u�n���Z���̐����Ƌ����ł���A�Z���Ƃ̌𗬂��d�������u�𗬊ό��v��i�߂�Ƃ��A���K�͂ȎY�ƂɐV���Ɏ�g�ށA�N�ƉƐ��_�̂���l�������x�����A�Y�Ƃ��N�����₷����������v�Ƃ��Ă���i�����AP27�j�B�@���g�b�v
�S�j1990(����2)�N�ɃI�[�v����������ҕ����Z���^�[�w�S�N���x�ɂ܂��A�n����T�[�Z�[�W�Ȃǂ����u�y���y���H�[�v�����݂��ꂽ�B1995(����7)�N8���A�V���ɏ�������҂𒆐S�ɁA���c�p���H�[�u�o�[�o���͂����v���J�X�B�u�����v�ƃJ�b�v���́u�v�̖��̂�p���l�[�~���O�̖��ŃA�s�[�����Ă���B�������Ǝ�I��̔w�i�ɂ́A�D�]�̃n���Ƃ̑g�ݍ��킹���悭�A�{�ݓ��̋i���X�ŏo������̂Ƃ̍l������u�p���H�[�v�Ƃ��铙�̌v��I�X�܌o�c��S�|���Ă���i�����B�j�B�@���g�b�v
�T�j�����A�iP27�j�B
�@
�@
[�n�����N�\]�@�@���g�b�v
�@
�m���K�҃f�[�^�n�@���g�b�v�@
�m�ό������n�@�@���g�b�v
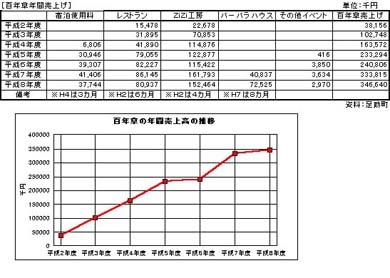
�@
|

�@�����������قƂ��Ắu�O�B�������~�v

�A�O�B�������~�̓������B�E���̊������̌����͈ڒz�B

�B�O�B�������~�̉��Â���

�C�����������Z���^�[�u�S�N���v�̑S�i

�D���������H�[���ް���ʳ��̓���

�E���N���ɂ���эH�[�u���������H�[�v

�F���������H�[�ƃZ�b�g�Ƃ��Č�Ő������ꂽ��ݍH�[�u�ް���ʳ��v
�@
|