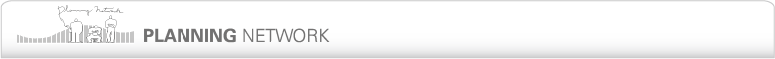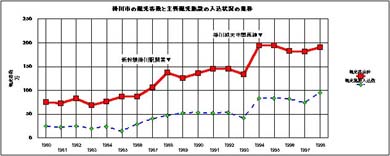| ①概況ときっかけ
②始動時期の特徴
③集客商品の特徴
④継続的取組み
⑤参考文献
⑥地域づくり年表
⑦来訪者データ
|
|
①地域の概況と地域づくりのきっかけ
掛川市は、山内一豊の城下町、東海道の宿場町として町の礎が築かれ、発展してきた。また、二宮金次郎(二宮尊徳)の報徳社の総本山も掛川に立地している。しかし明治以降の近代化の中で、故郷を離れ東京に向かうという「向都離村」の志向1)が強まり、人口の低迷・地域活力の低下が、まちづくりの重要テーマとなっていた。
昭和52(1977)年に市長に就任した榛村市長は、これまでの5期(現在6期目)の政権の中で、ユニークな地域づくりの取組みを展開し、選択して地域にとどまる住民(選択性土着民)を増やし、市民のやる気を掘り起こして活力を取り戻すとともに、全国的にも知名度を高め「パイロット自治体」と称されるまでに地域イメージを高めてきた。
まず、全国に先駆けて「生涯学習都市宣言」を行い、全国に「生涯学習」という言葉とシステムを定着させることからはじめ、市長自らが『夢シリーズ三段飛び2)』と呼ぶ、①新幹線掛川駅、②東名掛川インター、③掛川城天守閣の再建(本格木造)を実現したことで、市民の共感・共有の気持ちを高め、また一方では新幹線掛川駅の設置を機に、観光客や企業の誘致を進める等、定住人口と交流人口の獲得の二つの取組みを段階的に展開している。
→トップ
②始動時期の特徴
始動期の掛川市の地域づくりは、①モデル定住圏(三全総)、②生涯学習都市宣言、③新幹線掛川駅設置の3つを旗印3)に進められる。
地域づくりのリーダーとなる市長は、就任3カ月後に、新幹線駅構想を発表し、市民に「夢」を語りかけている。また、翌年には国土庁から「モデル定住圏」の指定を受けると同時に、<地域にもっと愛着をもってもらう、そのためには地域をもっと知ることが大切>との考えのもと、杉田玄白の蘭学事始からヒントを得て、『掛川学事始』を提唱、広報に「市長レポート4)」と題して市長の考えを広く市民にアピールしている。さらに翌年には、全国初の「生涯学習都市宣言」を発表。全国的にも「地方の時代」と言われ始めた時期であったこととユニークな取組みであったことから、マスコミを通じて全国に掛川市の名を広めることとなる。
生涯学習をキーワードに、「生涯学習10カ年計画(1980~1989年)」をスタート。中央(国)から助役を招聘して地域づくり(都市づくり)の智恵を得ている。また、最初の10年間は、地域住民との対話を大切にし、生涯学習センター、学校教育施設の充実、市立病院の改築、区画整理による都市づくり等、モデル定住圏の中核都市として身近な生活環境づくりを実施している。
その一方で、新幹線駅設置への働きかけを行い、昭和59(1984)年に設置決定、市民からの募金5)、周辺市町村(モデル定住圏の圏域)からの協力により、昭和63(1988)年に『夢』と言われていた新幹線駅を開業することとなる。生涯学習から始まる掛川市の地域づくりは、新幹線駅開業により一つの段階を完成させたものと考えられる。 →トップ
③集客のための商品の特徴
『夢』が現実のものとなると連鎖反応として構想が広がる。新幹線駅開業の決定は、企業誘致(エコポリス)を円滑に進めることに貢献する。また、新幹線という太い交通のパイプがつくられたことにより観光客の増加も期待され、各種の観光関連施設が次々と企画・開業される。その中で、掛川市の地域づくりの鍵を握る集客施設は、『掛川城』の再建である。
榛村政権の前任市長時代からの懸案であった掛川城の再建は、財政負担の関係から先送りされていたものであり、地域住民にとっての掛川城再建は、単に観光客誘致といった側面だけではなく、地域のシンボルづくりを意味していた。榛村政権になってからも、城址にある御殿の重要文化財(国)指定、城址公園の整備の実施等、再建に向けての手立てを打ってきた結果、財政力の向上、市民からの募金6)も追い風となり、本格的木造構築物として再建に至る。また、天守閣周辺の市街地では、年間40万人の集客力のある天守閣を核に「城下町風の街づくり(区画整理)」の推進、観光関連施設の整備等、積極的な集客を図り、郊外店に押されつつある中心商業地の活性化にも効果を得ようとする取組みもなされている。
新幹線駅開業から始まる掛川市の地域づくりは、エコポリス(工業団地)への企業誘致、東名掛川インターの開業を経て、掛川城天守閣の再建により、次の段階の地域づくりを完成させたものと考えられる。
→トップ
④継続的取組みの特徴
掛川市の集客型地域づくりの特徴は、不特定多数の人の力だけに頼ろうとするものではない。あくまで地域活力は、地域に住まう<選択性土着民(住民)>の地域を愛し、誇りに思う気持ちを基礎としている。その上で、優良企業の出張族や観光客等の交流人口のもたらす経済的効果、文化的刺激を地域全体で共有しようとする考えでの取組みを次のステップでのテーマとしている。
1990年から始められている「生涯学習10カ年計画パートⅡ」では、心の問題を最重要課題とし、<考え深い市民=住民が地域づくりを我が人生設計とともに考える>による地域づくりこそが、継続・発展の原動力であると考えているように思える。 →トップ
[参考文献]
①榛村純一(1997)『わがまちの活性化戦略』、清文社
②榛村純一(1998)『まちづくりの極意』、ぎょうせい
③榛村純一(1995)『分権の旗手-飛躍する小都市』、ぎょうせい
④榛村純一(1993)『地球田舎人をめざす』、清文社
⑤榛村純一(1998)『よみがえる二宮金次郎』、清文社
⑥榛村純一(1992)『小都市15年の生涯学習まちづくり』
地域の活力と魅力<P313~331>ぎょうせい
⑦榛村・若林(1994)『掛川城の挑戦』、静岡新聞社
⑧榛村純一(1978~)『市長レポート・掛川学事始』、広報誌コピー(掛川市より資料提供)
⑨榛村純一(1993~)『市長の寸感千字』、広報誌コピー(掛川市より資料提供)
⑩掛川市(1992) 『第三次掛川市総合計画』 他「総合計画」のレビュー等
⑪掛川市史編纂委員会(1995)『掛川市史(近現代・資料編)』 他<上巻><中巻><下巻>
⑫掛川市教育委員会(1996)『掛川城のすべて』
⑬亀地宏 (1984)『生涯学習都市-静岡県掛川市』
むらおこしルネッサンス<P168~176>、ぎょうせい
⑭川俣芳郎(1985)『生涯学習運動の推進』
変革時代のまちづくり・むらおこし<P121~125>、ぎょうせい
⑮本間義人(1994)『掛川市の土地条例』、まちづくりの思想<P298~303>、有斐閣選書
→トップ
[注釈]
1)明治5年の福沢諭吉の「学問のすすめ」以来、『都に向かって村を離れる学校教育偏重の精神』となったと榛村氏は見ており、このことを『向都離村』と称している(文献①P18)。 →トップ
2)榛村氏は、日本の歴史の中で、都市化の波は、①戦国から江戸初期、②明治維新後、③第二次世界大戦の3回あったとし、掛川の場合は、第1回の都市化の波では「山内一豊」の10年、第2回と第3回は波に乗れず、ここ15年のまちづくりが城下町建設以来の地域づくりであるとしている。その最大成果として、①新幹線掛川駅、②東名掛川インター、③木造天守閣復元の3つの事業を掲げ、これらを『三段跳びの夢シリーズ』と称している(文献⑦P12)。 →トップ
3)市長レポート・掛川学事始(No103、1982年9月15日号) →トップ
4)市長就任後の翌年度、昭和53年度(1978年4月)から『市長レポート・掛川学事始』を広報誌に自筆寄稿している。途中、療養のために休筆したものの、平成5年12月からは、新しく『市長の寸感千字』として20年間にわたって自らの考えをアピールしている。 →トップ
5)新幹線駅設置には、120億円の費用が必要とされた。概略の費用負担配分は、静岡県が1/3、市が1/3、その他周辺市町村で1/3であり、市分担の約40億円は、市の財政拠出金から20億円、市民募金が20億円と考えられていた。市民募金に対して、市長は『広報(市長レポート・掛川学事始)』の中で、①5年から10年後への投資、②子供の教育費のように愛と希望をもって、③一肌脱ぐの精神(喜捨・御祝儀)、④民間活力の注入・行財政参加としての募金、⑤共同の財産づくりの5つの納得の仕方を示して募金を呼び掛けている(広報1984年11月1日号)。1984(昭和59年)6月に開始した「こだま貯金」は、同年12月に「1億円突破」、翌年3月に「10億円突破」し、1986(昭和61年)2月には「20億円」を達成した。 →トップ
6)1987(昭和62)年に掛川に転入された白木ハナエさんが、名刺代として、生涯学習施設基金に1億5千万円寄付されたことから、にわかに天守閣復元が現実化する。この経緯については文献⑥のP15~17が詳しい。また、掛川市では、これまでの大プロジェクトに対して、合計55億円の募金や出資という、民間活力の導入に成功しているという(文献①P69)。→トップ
[地域づくり年表] →トップ
[来訪者データ] →トップ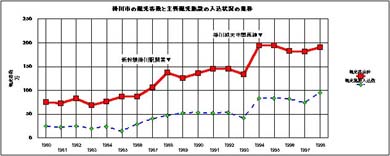
|
|

①1994年に掛川城天守閣を木造で再建。建築物としての許認可が得られず、構造物として再建。

②新幹線の最終列車が通過するまでライトアップされている掛川城。

③御殿からみた掛川城。

④御殿の全景。

⑤復元された大手門と掛川城。

⑥1995年に復元された大手門

⑦掛川城周辺では、地区計画により「城下町風まちづくり」を推進。写真はカメラ店であり、「掛川藩御用達」が笑いを呼ぶ。

⑧城下町風まちづくりの一角のポケットパーク

⑨新幹線ホームからみた南口駅広場。新幹線の駅前としては他に見られないユニークな事例。

⑩掛川駅南口の全景

⑪掛川駅北口駅前広場

⑫駅天守閣ギャラリー。かつては22Mの木レンガの駅前道路として注目された道路。

⑬駅構内の「これっしか処」。広域の物産展示施設・ショールームとして機能している。小さな「っ」の持つ意味が大きい。

⑭掛川城のななめ向かいの休み処、食事処、土産処である「こだわりっぱ」。

⑮二宮尊徳の精神「報徳精神」の拠点・大日本報徳社

⑯大日本報徳社の正門.左が経済門,右が道徳門.経済と道徳の両方が必要と説いている。

⑰大日本報徳社内部

⑱大日本報徳社の淡山翁記念報徳図書館

⑲徳育おにわふみいし。資生堂の開発した健康遊歩道が市の健康施設の中庭に寄附されている。

⑳1993年に東名掛川インターが開業。開発インターであり、ゲートは城下町風に整備。

21掛川の名を全国に知らしめた『生涯学習都市』の拠点である掛川生涯学習センター。

22線路側からの市庁舎外観

23市庁舎内部。木を使って温かみを表現するとともに、開放的な市役所となっている。

24企業博物館となっている資生堂の『ARTHOUSE』

25資生堂アートハウス前の「健康遊歩道」。健康遊歩道は資生堂の特許。

26新ねむの木の里。

27ねむの木の里の一角に整備された「吉行淳之介文学館」

28粟ケ岳山頂からの展望

29粟ケ岳山頂に向う沿道には茶畑が広がる。

30中山峠の茶屋。

31エコポリス(工業団地)内に立地しているTANIYAサーキット

32加茂荘あやめ園

33総合教育センター
|