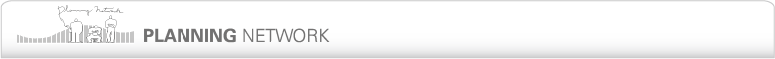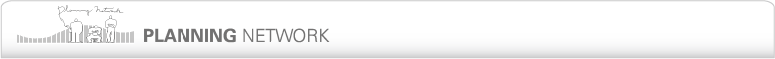| はじめに
まちぐるみ博物館は
こうして生まれた
まちぐるみ博物館とは
まちぐるみ博物館の
取り決めごと
多くの来館者からの
エールが地域に自信
を与えた
おわりに
参考資料
|
|
はじめに
夜7時。店じまいをし、夕餉の準備をするや否や、おかみさん方が町並み交流館に集まる。「旦那衆は集まる機会があるがおかみさん方にはそのような機会が無い」という素朴な疑問から生まれた任意な集まり。佐原のまちなかでの様々な出来事を教材とした勉強会から始まった「佐原おかみさん会」が、平成17年8月末に、佐原のまちづくりにおいてエポック的な事業をスタートさせた。佐原まちぐるみ博物館である。事業企画や取組み内容そのもののユニークさに加え、これからの時代を象徴する「水平展開のまちづくり〜市民主役のまちづくり」を実践するための手法がこの取組みの中には凝縮されており、佐原のまちなかで展開される今後の事業展開において規範・モデルとなることを予見させるものとなっている。 →トップ
まちぐるみ博物館はこうして生まれた
平成8年、関東で初めて伝統的建造物群保存地区に指定された佐原は、江戸中期以降に、水運を利用して「江戸優り」と言われるまでに栄えた地域であり、江戸時代の店構えを残す店舗や昔の道具類を大切に伝えてきた家が多く、当時の面影を今なお残している。東京都心から車で約90分という交通条件と、第二次のまち歩きブームとが相まって、観光地ではなかった佐原のまちなかには、年間約35万人のお客さんが訪れはじめている。
まちなかを流れる小野川と由緒ある香取街道沿いには、江戸を彷彿とさせる佇まいが見られ、そこに住まう人々の努力が「江戸優り」の統一イメージを外観から維持・再生してきた。佐原の本当の良さは、この「江戸優り」を大切にしてきた暮らしぶりそのものにある。佇まいの中に一歩足を踏み入れ、伝統的な各商家の構えや商売する上での家訓・商品揃えの目利き、いまも大切に使っている様々な道具類の向こうにあるもの〜目には見えない伝統がおかみさんの案内を介した時、目の当たりに広がってくるのである。
「訪れられた多くの方々に佐原をもっと知っていただきたい」という願いが形として、またシステムとなって表れたものが『佐原まちぐるみ博物館』である。お雛さまや五月人形などを数箇所の商家で展示する取組みが数年前から始められていたが、それを「まちぐるみで展開してみよう」「まちなか全体を博物館のようにしてみよう」との思いに広がってきた。もちろん、この企画・構想を温めてきたのは、まちなかのおかみさん方が集まる佐原おかみさん会での話し合いの場でのことである。
「1時間程度の一時立寄り型の来街者が多い」「まちなかでの回遊がみられない」「食べるところや見処が少ない」などの地域としての課題、それへの挑戦もあった。この取組みに対して、平成17年度、国土交通省の都市観光の推進による地域づくり支援事業がバックアップ。佐原のまちなか活性化の方向性を多角的に検討する佐原戦略ビジネス事業推進協議会・委員会、佐原市、千葉県等の協力体制も整えつつ、主体的・実践的には佐原おかみさん会が中心となって事業に取り組むための舞台とシナリオ、そして演者が整った。 →トップ
まちぐるみ博物館とは
佐原まちぐるみ博物館は次の5つのことを基本とする新しい形態の博物館である。
① 各家(商家、飲食店等)の自慢の逸品を見せびらかす場である。
② 展示物は、形あるものばかりでなく、自慢の味や長年培った技等も含まれる。すなわち、まちぐるみ博物館とは、地域の伝統の技や文化に身近にふれることのできる場である。
③ まちぐるみ博物館は観光施設ではなく、新しいかたちの生きた博物館である。
④ まちぐるみ博物館の館長・楽芸員はおかみさんやオーナーである。
⑤ 暮らしと自慢こそが、まちぐるみ博物館の展示品である。
まちぐるみ博物館は、単に滞在時間の延長化、来街者の回遊範囲の拡大のためだけに実施したものではない。商家の主やおかみさん、すなわち各博物館の館長や楽芸員が来館者に対して博物館の展示品を案内することを通じて、まちなかで商売をする人の誇りや自慢を育てること、来館者の佐原に対する不満を聴き取り地域の魅力の品質管理に活かすこと、市民が主役・もてなしの提供者であるという意識をまちぐるみで展開すること等、まちぐるみでの様々な活動を試行的に展開するためのきっかけとすることを企図したものである。
昨年の8月末28館の参加でスタートしたまちぐるみ博物館が、11月末には33館、現在は40館を越そうとしている。おかみさん方の熱心な取組みが、まちなかの方々の心に火をつけ、志と意が伝播してきているのである。 →トップ
まちぐるみ博物館の取り決めごと
江戸時代よりまちづくりは住民がルールをつくり実践してきた地域、それが佐原である。まちぐるみ博物館を運営するにあたり、おかみさん方は、①運営主体、②展示品ラインナップ、③合意の手続きと新たな展示品の登録、④各博物館の運営と展示方法、⑤来館者をもてなす際の留意点、⑥広報ツール・PR、⑦来館者の生の声の把握とそれを活かしたおもてなし向上の7つの項目について取り決め、それを『佐原まちぐるみ博物館口伝帖』として記した。さすが家訓を継承してきた地域の伝統が現代にも生きている。「口伝帖」であるので詳述はできないため、読者には是非一度足を運んでもてなしを体感し、口伝帖の内容をおかみさん方から聞き出していただきたい。 →トップ
多くの来館者からのエールが地域に自信を与えた
まちぐるみ博物館のオープンから3ヶ月間、おかみさん方自らが調査員となり対面形式の聴き取り調査によって来館者の生の声を収集した。分析の結果は『来館者からの通信簿(つうしんぼ)』として取りまとめられ、早速「佐原おかみさん会」の教材となった。紙面の関係で詳述できないが、その中には新たな発見がいくつか見られた。
その一つがリピーターの捉え方であった。今回の対面調査では、来る前の印象と来てからの実感を100点満点で評価いただき、その差から満足顧客、納得顧客、不満足顧客という3つのグループに来街者を区分、各タイプ毎に志向性の違いを見ることから、不満足顧客を満足顧客へと導くための方策を探ろうとした。解析していく過程で2〜3度目の来街者に不満足顧客が多いことが分った。佐原はリピーターが多いことは既往調査からも分っていたものの、実はその裏に大変大きな落とし穴があることを見い出したのである。2〜3度目の来街者は、以前の良好な印象が思い出とともに高まりをみせ、大きな期待となって来佐されることから、その大きな期待に応えられないと、本当のファンになっていただけない、いわば離反顧客となってしまうということである。このことから、通常言われているリピーターを佐原おかみさん会では、「リピーター(2〜3度目の来街者)」と「佐原ファン(4度以上の来街者)」とに分けて捉え、それぞれの方々が求めている期待は違いがあることを知った上でのもてなしを展開することの必要性を改めて確認したのである。
もうひとつの発見は、来館者の方々の印象から得られたものである。調査では、佐原の交通、情報提供、まち全体の魅力・雰囲気、施設的な魅力、商品の魅力、もてなしに関する15の項目について、5段階で評価いただいた。言わば来館者からの通信簿である。結果は、初めての来街者の評価は高く、日常的に接している地域住民からの評価は辛口であった。しかし、まちぐるみ博物館に対する評価と、佐原のまちの人々のもてなしに対する評価は、地域住民を含むいずれの来館者からも高い評価が得られた。地域住民のからも受け入れられたことは、まちぐるみ博物館を運営している佐原おかみさん会のメンバーの方々にとって大きな自信となった。自分たち一人ひとりのもてなしは小さな力でしかないが、それらが束になった時に大きな力となって現れる〜多くの来館者からのエールはおかみさん会の活動を新しい取組みへと展開する原動力となっているのである。 →トップ
おわりに
佐原まちぐるみ博物館は新しいステージに向かいつつある、目下の検討課題は「変わることと変わらないこと」。「あの展示物にまた会いたい」と、お友達をつれて越しになるお客さんにも、「こんなのもあったの」と新たな展示物に目を輝かしていただけるお客さんにも満足していただきたい。佐原おかみさん会の次なる挑戦は、お客さまの満足感を維持・向上するための手法を磨くこと。お正月飾り、お雛さまめぐり、五月人形と、常設展とは別の企画展を次々と企画・構想し、実践する体制に入っている。絶えず新しい発見のあるまち・佐原、おかみさん方の「お元気でしたか」「お帰りなさい」という声が、小江戸のまち角から、今日も聞こえてくる。 →トップ
立教大学観光学部兼任講師
大下 茂 氏 寄稿
[参考資料] →トップ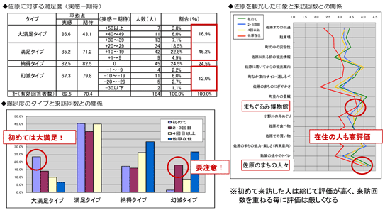
来館者200人以上の声を分析し、佐原のまちぐるみ博物館と佐原観光の品質管理に生かした(国土交通省の都市観光の推進による地域づくり支援事業の調査結果より)。
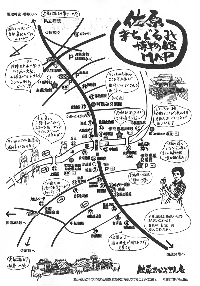
佐原まちぐるみ博物館MAP。手づくりのマップももてなしの一つ。参加の申し込みは増えつつある。
|
|

① おかみさん会の開催風景

②まちなかを流れる小野川。行き交う舟がゆったりとしたときの流れを映し出している

③各商家の自慢の逸品が展示されている。誇りや自慢が佐原まちぐるみ博物館の展示品
(写真;佐原市提供)

④今年のお正月には軒先にお正月飾りを展示。各商家の個性的な彩りが、往来する来街者との会話を生み出した。

④今年のお正月には軒先にお正月飾りを展示。各商家の個性的な彩りが、往来する来街者との会話を生み出した。
 ⑥佐原おかみさん会のリーダー達がフォーラムで取組みの概要をPR(写真;佐原市提供)。 ⑥佐原おかみさん会のリーダー達がフォーラムで取組みの概要をPR(写真;佐原市提供)。
|